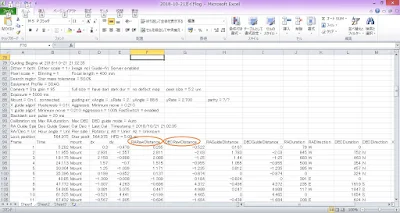オートガイド ログファイルの解析
10月21日のオートガイド状態を、ログファイルから解析してみました。
PHD2ガイディングは、何らかの操作をすれば、その都度ログファイルに
そのデータが記録されて残りますが、キャリブレーション、オートガイド
動作の記録も当然ログファイルを開いてみることができます。
ログファイル(ガイドスタート部分を表示)
カンマ付きテキストなのでExcelで読み込む。(ガイドスタート部分を表示)
ここで解析に必要なデータ項目は次の2つです。
•RARawDistance:キャリブレーション結果から計算された、赤経方向のガイド星のズレ。
(単位はピクセル)
•DECRawDistance:キャリブレーション結果から計算された、赤緯方向のガイド星のズレ。
(単位はピクセル)
これを
プロット(グラフ視覚化)してみました。
まず、
ガイド星が赤経、赤緯のどちらの方向にどの程度流れ、どのタイミングで修正が
入ったかを見てみます。
図1)キャリブレーション終了直後の、ガイド状態(約15分間)
赤経方向(赤線)は、0を挟んでプラス、マイナスと繰り返し修正が入っていることが
分かります。
平均値を計算すると約「+0.4」ピクセルで、ズレはおおむね0です。
一方、赤緯方向(青線)は、最初の1分間は極端なズレですが、それ以降はほぼ
一定方向にズレていった後に、修正が入っていることが分かります。
これも、平均値を計算すると約「+0.2」ピクセルです。
図2)ガイド動作途中で、構図合わせ後のガイド状態(約10分間)
次に、
ガイド中にガイド星がどのように動いたかを見てみます。
図3)キャリブレーション終了直後の、ガイド状態(約15分間)
ガイド星の位置は、ほぼ±2ピクセルの範囲ですが、プラス値の赤経方向に
偏っていることが分かります。これは、極軸の未調整のズレと思います。
図4)ガイド動作途中で、構図合わせ後のガイド状態(約10分間)
今後は、できれば60分以上のガイド状態について検証したいと思います。